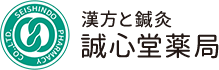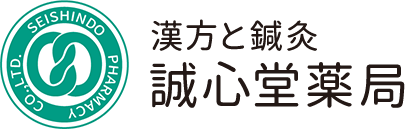店舗お知らせ
- 銀座
- 2024/11/05
朝の疲れ・・・体のサビが原因?
寝ても疲れが取れない・・・そんな積み重ねの疲れに悩まされている方も多いのではないでしょうか。
その背景には体のサビ(脳疲労)が隠れているかもしれません。
そもそも体のサビとは、脳内で発生した活性酸素によって細胞が「さびる」(酸化)ことが原因と考えられています。
もう少し詳しいお話をすると、脳内で働いている自律神経は、身体機能を維持するために常に働いています。
そのため酸素の消費量が非常に高く、大量の活性酸素が生じます。
その脳内で発生した活性酸素は、神経細胞を攻撃します。
具体的には細胞のエネルギー工場であるミトコンドリアを傷つけて(酸化させる)、サビつかせてしまいます。
このサビが疲労の正体であり、サビにより自律神経の機能が低下した状態が疲労となり、
サビがこびりついて取れなくなった状態(元に戻らなくなった状態)を老化と呼びます。
ストレスや睡眠不足、食品添加物、環境汚染により活性酸素が過剰に増え脳の細胞が酸化ストレスによって傷ついているにも関わらず、修復が追い付いていないことです。
そのことにより細胞が酸化されてしまうと内臓や皮膚、骨などあらゆる組織にダメージを与え、老化やガン・生活習慣病の原因となります。
では漢方薬では何ができるかというと活性酸素を除去したり、老化のスピードを遅らせたりする効果があります。
また、血流の流れを改善する活血薬や、血流の流れが滞って巡りが悪くなった状態の瘀血薬など、個人によって選ぶ漢方薬は変わってきます。
長年悩まれているという方はそのままにせず、ご来店くださいね。
その際はご予約が必要となりますのでご予約お待ちしております。
- 銀座
- 2024/10/14
潤いチャージ!!早め早めの乾燥ケアを。
日中の暑さが少し残りますが、日が短くなり朝晩はだんだんと涼しくなりましたね。
蒸し暑くジメジメとした空気から急に冷たく乾燥した空気に変わり、
身体の内も外も乾燥のダメージを受けやすい時期です。
中医学では、乾燥の邪気を燥邪といい、秋の臓といわれる「肺」は乾燥を嫌います。
燥邪は主に口と鼻から侵入し、肺にダメージを与えて、身体の中の潤いを消耗させます。
すると、咳や風邪のような呼吸器症状だけでなく、肌の乾燥やかゆみ、髪のパサつき、便秘のような不調を引き起こしてしまいす。
乾燥の季節を乗り切るには、「肺 」「からだ」「肌」を潤すこと、保湿することが大切です!
身体の内側「肺」を潤すために白い食材を食べましょう!
長いも、れんこん、百合根、梨、大根、豆腐
豆乳、はちみつ、白ごま、、、
「からだ」や「肌」を保湿するにはスキンケアがおススメです。
誠心堂オリジナルスキンケア「爽肌精」が素肌強化キャンペーンを実施中!!
気になる方はぜひお問い合わせください。
https://www.seishin-do.co.jp/news/?ca=3&p=1#n_1726284038-155151
早め早めの乾燥ケアをし、潤いチャージをしていきましょう!
- 銀座
- 2024/10/02
ストレートネック・スマホ首って?
ここ近年で耳にする【ストレートネック】や【スマホ首】聞いたことありますか?
正常であればS字に湾曲している頸椎が、カーブが減ってしまいまっすぐに伸びてしまっている状態をストレートネックといいます。
スマホやパソコンを使うときに首が前に出ている姿勢が続くことが主な原因となっていることで、スマホ首と呼ばれることもあります。
頭の重さは体重の10分の1くらいの大きさといわれています。その重い頭を支えるために首周辺の筋肉にかなり負荷がかかります。
悪い姿勢(顎が前に出て、首の後ろも前も筋肉が縮こまってしまい、顎が引けなくなってしまっている状態)や長時間同じ姿勢を続けることで、
猫背になってしまい、肩こりや目の疲れ、頭痛、手のしびれ、めまいや吐き気が治らないなどその首が原因となり自律神経を乱れさせているかもしれません。
それにより呼吸も浅くなり、内臓の働きにも影響を及ぼしてしまいます。
また顔のたるみや二重顎にも繋がってきます。
同じ姿勢がどうしても続いてしまう場合は、
1時間に1度肩や首を回す
立ち上がる習慣を身につける
首を伸ばすストレッチ
などをしてみましょう。
日常的に枕を見直すことや、お風呂に使って筋肉をほぐしてあげることもお勧めです。
それでもなかなか改善しない場合は、鍼灸治療や骨盤調整が必要です。
付随して起こる頭痛や吐き気、自律神経の乱れには漢方も効果的です。
ぜひお困りの方は1度当院へご相談ください。
- 銀座
- 2024/09/16
秋バテ対策をしよう!~気持ちよく秋を過ごすために~
夏の激しい暑さが少しずつ落ち着き始めましたが、まだまだ蒸し暑さは残っていますね。
少し過ごしやすくなってきたかと思った矢先、身体がだるい、頭が重い、疲れが取れない、冷えるといった症状を感じていませんか?
これらの不調を最近では秋バテといい、現代病の一つとも言われています。
夏場に冷たいものを取りすぎた内臓冷えやエアコンと外気の温度差による冷房冷えが原因となり、
身体は自分が思っている以上にストレスを感じています。
これにより自律神経が乱れると身体の機能を正常に調整することができず不調を感じやすくなります。
夏の不調や弱った身体が十分に回復しないまま秋を迎えると、
雨や台風など気象の影響でさらに自律神経が乱れ、秋バテの症状が出てきます。
中医学では秋バテを身体のエネルギー不足=気虚によって起こりやすいと考えられます。
例えば、夏の暑さや室内外の気温差に対応するためにいつも以上に気を消耗したり、
冷たい飲食物の摂り過ぎで胃腸機能が低下し、気を十分に作れないために気が不足してしまいます。
日々の食事で気を補う食材を取り入れ、秋バテ対策をしてみましょう!
【気を補う食材】
山芋、じゃがいも、カボチャ、しめじやしいたけのようなキノコ類、
オクラ、鶏肉、白米、大豆など、、、
そのほか生活習慣を見直し、自律神経を整えることも大切です。
・エアコンで体を冷やし過ぎないために温度調整をする
・お風呂にゆっくりと浸かる
・適度な運動やストレッチをする
・栄養バランスが整った食事をとりいれる
身体は資本ですので、自分に優しく身体を労りながら楽しい秋を過ごしましょう!
- 銀座
- 2024/09/05
口内炎
口内炎ができると地味に痛いですよね。
そもそもなぜできるのかというとストレスや疲れ、ビタミン不足や物理的な刺激、ウイルスによる感染などさまざまな原因が考えられます。
中医学では脾胃の状態や、体に熱がこもる【熱邪】というのが体に溜まることで起こるといわれています。
【胃熱】暴飲暴食や辛い物や味の濃い物、脂っこいものなど食べていると、それらが原因で熱邪が生じて口内炎になります。
【肝火】肝は五臓六腑の中でも、体の中の機能や精神や情緒などを調整する機能です。
この肝の機能がストレスや激しい感情の起伏などで乱れると、熱邪が生じて口内炎になります。
【陰虚】胃熱や肝火が長い状態続くと、体の中の体液などの陰液が消耗され、陰陽バランスを崩し、熱邪が生じて口内炎になります。
【気虚】気が不足して熱のコントロールがスムーズにできなくなることで、口内炎が生じます。
色々なパターンや、体質・その時の状態によって選ぶ漢方も変わってきます。
よくできやすい方はそのまま放置などせず、1度体質を見直してみてはいかがでしょうか?