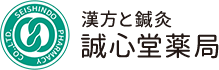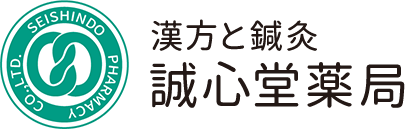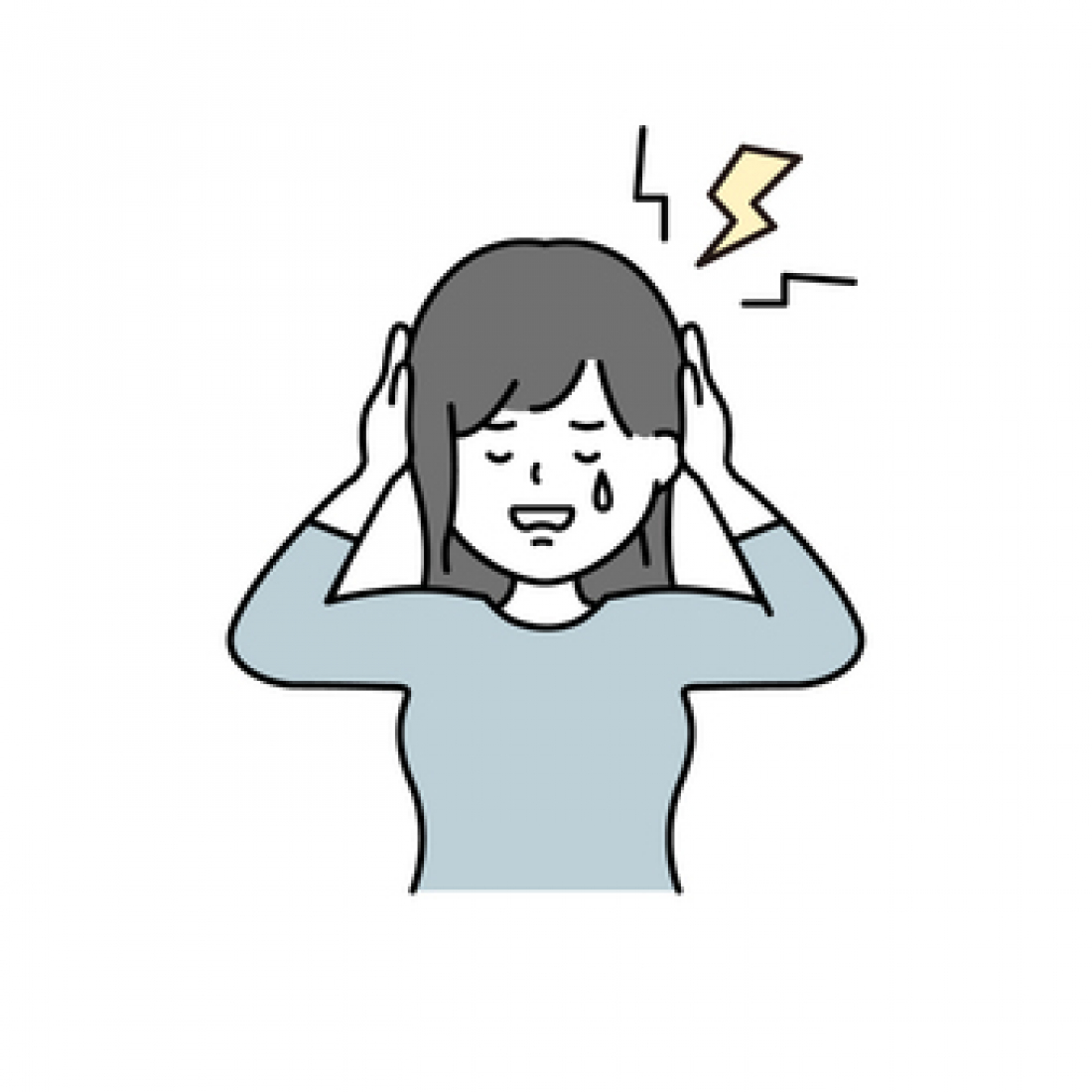
店舗お知らせ
- 銀座
- 2025/05/04
ズキズキ・ガンガン~辛い頭痛の対処法~
頭痛は、慢性頭痛である片頭痛・緊張性頭痛・群発性頭痛の3タイプ分類され、天気痛というものも最近言われるようになってきています。
片頭痛:ズキンズキンと脈打つような痛み。女性に多く、吐き気や嘔吐を伴うことも。
緊張型頭痛:頭全体が締め付けられるような痛み。過労・ストレスなどが原因で起こります。
群発性頭痛:片目の奥の激しい痛み。男性に多くみられ、数週間から数か月頭痛が続きます。
天気痛:雨の日や低気圧時などに起こる頭痛。
中医学では、慢性化したり繰り返したりする場合は、体内に不調があり、頭痛が起こりやすい体質になっていると考えます。
肝うつタイプ:ストレス頭痛、
気血不足タイプ:疲労で頭痛が起こりやすい
腎の虚弱タイプ:疲れると頭痛がする、慢性頭痛
痰湿タイプ:頭が重く痛い、雨の日に頭痛がする。
瘀血タイプ:刺すような頭痛、ズキズキする頭痛
に分けられます。
頻繁に起こると仕事や生活にも支障が出てしまうので、頭痛に悩まされている方は積極的に体質を改善していくようにしましょう。
また暮らしのケアとして、適度な運動で気・血の巡りを促しましょう。日常に楽しみを見つけて上手にストレス発散し、食生活を整え、暴飲暴食は控えましょう。入浴をして温まり、十分な睡眠をしっかりとりましょう。
それでもなかなか改善しないという方は、漢方や鍼灸治療がお勧めです。
1度ご相談くださいね(^^)
- 銀座
- 2025/04/21
油断は禁物!~紫外線疲労に気を付けよう~
ようやく気温が上がり、春らしさを感じる日が増えましたね。
お出かけの機会が増える季節ですが、その時に欠かせないのが“紫外線対策”です。
紫外線は3月ごろから急激に強くなりはじめ、真夏前の5~7月頃にピークを迎え、9月頃まで強い状態が続きます。
長い時間日光に当たると、運動をしていなくても「疲れた」と感じたことはないでしょうか?
実は目から入る紫外線の刺激は、脳へ伝わり全身に影響して大量の活性酸素=疲労物質を作り出してしまいます。
すると体は酸化ストレスを受け、自律神経が乱れる、消化機能の低下、ぐったりするほどの疲労感などにつながってしまいます。
紫外線からの疲労を軽減するには、
①抗酸化力が高い食材をとる②紫外線を浴びないようにすることが大切です。
① 抗酸化力が高い食材
トマト、キャベツ、大根、黒豆、黒ゴマ、ブルーベリー、なす、ブロッコリー…
元気を補う=補気の食材を組み合わせられると疲労回復にGOOD◎!
山芋、じゃがいも、かぼちゃ、大豆、枝豆、米、玄米、豚肉…
② 紫外線をシャットアウト!
日傘や帽子、サングラスの着用
日焼け止めを数時間おきに塗る
内からも外からも紫外線対策をしましょう!
- 銀座
- 2025/04/16
春の睡眠の乱れ
春は寒暖差が激しく、環境変化や花粉症によるストレスなどが原因で、睡眠の乱れが出やすくなります。
そのことにより、交感神経・副交感神経のバランスがうまく取れなくなり、【自律神経が乱れる】ことで、睡眠が上手く取れなくなったり、昼間眠くなったりとしやすいです。
睡眠は7時間が理想とよく耳にしますが、睡眠時間は人それぞれ違います。
そんなに寝なくても日中元気に働けるという方は、十分な睡眠がとれていますが、たくさん寝ているのに日中眠い、寝足りないという方は不眠となります。
寝入ってから3時間の間に深い眠り(ノンレム睡眠)に達すればぐっすり寝たという状態になるので必ず7時間必要ということではないのです。
では睡眠がなぜそんなに必要なのか?寝ている間に細胞の修復をし、脳や体、皮膚を休ませ、疲労回復や免疫機能の増加・記憶や感情の整理などもしてくれます。
睡眠のリズムが崩れることで体への影響がすぐに現れてしまいます。
なので(睡眠時間<睡眠の質)が大事になってきます。
中医学では【肝】の働きが亢進しやすく、そこが疲弊すると血を消耗してしまうためと言われています。
食事の摂り方や、入浴の仕方、寝る前の過ごし方なども非常に重要になってきますが、
それでも改善しない、寝付きが悪い・途中起きてしまう・夢をよく見て寝た気がしないという方は1度漢方相談や鍼灸治療をお勧め致します。
ゴールデンウィークを楽しく過ごせるよう、今のうちに身体を整えていきましょう!
- 銀座
- 2025/03/25
春は解毒(デトックス)の季節~ファスティングをはじめよう~
新年度が近づき、暖かい日が増えていますね。
冬の間は代謝機能が低下し、老廃物が身体の中に溜まりやすくなります。
さらに運動量も少なくなる傾向があるため、汗をかきにくくなり、体内の老廃物をうまく排出できずどんどん蓄積してしまいます。
老廃物が順調に排出されれば問題ありませんが、身体に溜まったままの状態が続くと、
体臭、口臭、便秘、肌荒れなど不調やトラブルの原因に...
なかでも冬の老廃物は体内に蓄積しやすく、その結果、春を迎える頃に「なんとなく不調」を訴える方が増えてきます。
春に起こりやすい不調として、のぼせ、めまい、便秘、肌荒れやニキビなどの肌トラブルが起きやすくなります。
中医学では、春は解毒作用(デトックス)が高まる季節とされています。
解毒の季節にあわせたキャンペーンを3/1から実施中!!
↓↓
「✨美血ファスティングキャンペーン✨」
https://www.seishin-do.co.jp/news/?p=1#n_1740981229-455640
ファスティングをすることで消化器官を休めることができ、体内に蓄積された老廃物の排出を促進することができます。
すると体内のデトックス効果が高まり、
身体のスッキリ感、肌の調子が良くなる、腸内環境が整うなど健康面でのうれしい効果が期待できます。
ただ痩せるだけでなく、身体の内側から「キレイ」をめざしませんか?
ファスティング、漢方、鍼灸など気になる方は、ぜひお問い合わせください。
- 銀座
- 2025/02/18
三寒四温を乗り切れる体に!
三寒四温とは2月の下旬~3月上旬の時期を表し、三日間ぐらい寒い日が続き次の四日間ぐらいが暖かいという日を繰り返されることを言います。
中医学では【肝】の季節とされており、自律神経のバランスが崩れやすくなるといわれています。
特に症状として、めまい・頭痛・イライラ・だるさ・眠気など自律神経の乱れが出ます。
そもそも【肝】とは、血液や気(エネルギー)など栄養を全身に巡らせ、自律神経を整える働きを担う臓器といわれています。
また、精神状態の安定や情緒の調節にも関与しています。
他にも、
・血液を貯蔵し、必要に応じて血の量を調節します
・肝血で全身を潤し、全身に栄養を与えます
・筋肉や腱を肝の血によって筋の働きを維持します
・目の働きを保つ
などがあり、肝の働きが低下するとエネルギーや栄養の巡りが悪くなり、情緒不安定やイライラ、落ち込みなどの症状を引き起こしやすくなります。
【肝の機能をよくする食べ物】
枸杞の実・貝類・セロリなどの香草・ニラ・山菜など苦みのある食材・豚肉・イチゴ・レモンなど
【三寒四温の時期の体調の整え方】
適度な運動を心がけて体温をあげるようにしましょう
身体を冷やさないようにお風呂に入るなど温めましょう
季節の野菜や果物、ビタミンCが豊富な食材をとるようにしましょう
睡眠をしっかりとりましょう
できるだけ心を落ち着かせリラックスできる時間を持つようにしましょう
心身のバランスを整えて快適に春を楽しく過ごしていけるようにしましょうね!