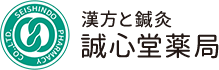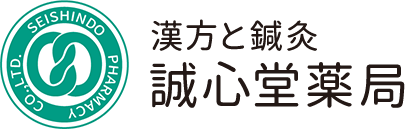肥満が腎臓に与える影響とは?GFR(糸球体濾過率)低下リスクとの関係
近年、肥満と腎機能低下の関連性 に注目が集まっています。特に、腎臓の機能を示す指標である GFR(糸球体濾過率) が、肥満によって低下する可能性があることが研究で明らかになっています。
世界規模の研究からわかった「肥満と腎機能低下」の関係
1970年~2017年 にわたる 47年間 のデータをもとに、世界40カ国の約560万人 を対象とした研究が行われました(BMJ, 2019)。この研究で、BMI(体格指数)とGFR低下リスクの関係が分析されました。
研究概要
- 対象地域:39の住民コホート、6つの高心血管リスクコホート、18のCKD(慢性腎臓病)コホート
- 対象者数:総計 約560万人
- 分析方法:BMI 25を基準として、それ以上のBMIでGFR低下リスクを比較
- 結果:BMIが高くなるほどGFR低下リスクが増加
| BMI値 | GFR低下 リスク (ハザード比) |
95% 信頼区間 (CI) |
|---|---|---|
| 25 (基準) |
1.00 | - |
| 30 | 1.18倍 | 1.09~1.27 |
| 35 | 1.69倍 | 1.51~1.89 |
| 40 | 2.02倍 | 1.80~2.27 |
この結果から、BMIが増加するにつれてGFR低下リスクが大きくなる ことがわかりました。特にBMI 35以上になると、リスクが約1.7倍、BMI 40以上では 2倍以上 になるというデータが示されています。
BMIについては過去記事「腎臓を健康に!一日に必要なエネルギーは?」
参照 https://www.seishin-do.co.jp/kidney/column_kato/011w/#toc_04
日本でも「肥満の多い地域=透析導入率が高い」傾向


日本においても、肥満の有病率が高い都道府県ほど、透析導入率が高い ことがわかっています。
この関連性は、日本透析医学会のレジストリ や 特定健診データ・医療費請求データ を活用した研究で示されており、肥満の多い地域では標準化透析導入比(その地域の人口特性を考慮した透析導入の頻度)が高くなることが明らかになっています。
つまり、肥満が慢性腎臓病(CKD)の進行を加速し、最終的に透析が必要になる可能性が高まる ことを示唆しています。
慢性腎臓病(CKD)とは?


CKD(Chronic Kidney Disease:慢性腎臓病) とは、以下のような疾患によって 腎機能が低下する状態 を指します。
- ◎糖尿病性腎症(糖尿病による腎障害)
- ◎慢性糸球体腎症(糸球体の炎症による腎障害)
- ◎腎硬化症(高血圧による腎障害)
現在、世界のCKD患者は6億人以上、日本では1,480万人以上 いると推計されており、「新たな国民病」 として警鐘が鳴らされています。さらに、CKDは年々増加傾向にあり、早期の予防と管理が求められています。
腎機能を守るために「肥満対策」が必須!


腎機能低下を防ぐためには、まず 肥満を解消することが重要です。
腎臓を守るための肥満対策
- ◎適正体重(BMI 18.5~24.9)を目指す
- ◎塩分を控える(1日6g未満が推奨)
- ◎たんぱく質の摂取量を適切に(腎機能が低下している場合は医師の指導に従う)
- ◎バランスの良い食事(野菜・果物・良質なたんぱく質を適度に)
- ◎定期的な運動(ウォーキングやストレッチなど)
- ◎水分を適切に摂る(脱水を防ぐため)
- ◎定期的な健康診断を受ける(腎機能をチェック)
腎臓は 一度ダメージを受けると回復が難しい臓器 です。そのため、早めの予防と健康管理が何より大切 です。
まとめ
- ◎肥満が進行すると、GFR(糸球体濾過率)が低下しやすくなる
- ◎BMIが高いほど、腎機能低下リスクも上昇(BMI 40で2倍のリスク)
- ◎日本でも肥満の多い地域では透析導入率が高い
- ◎CKD(慢性腎臓病)は「新たな国民病」として増加中
- ◎腎機能を守るには、肥満を解消し、生活習慣を改善することが重要
腎臓の健康を守るために、日々の食生活や運動習慣を見直し、適正体重を維持することを心がけましょう!
参考文献
BMJ. 2019 Jan 10;364:k5301.
https://www.bmj.com/content/364/bmj.k5301
更新日:2025-04-09