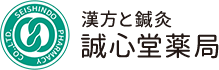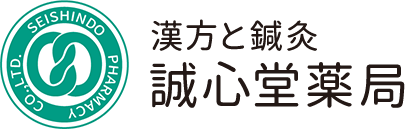腎臓病が気になる方の塩分計の使い方と塩分量の計算方法について
塩分摂取量の管理は、腎臓病予防や高血圧対策において重要です。特に、日常的に摂取する味噌汁やスープなどの汁物に含まれる塩分量を把握することで、適切な減塩対策が可能になります。
塩分計の使い方、測定結果から実際の塩分量を計算する方法、一日の塩分摂取目安、塩分濃度の基準について解説します。
1日の塩分量の目安
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、1日の塩分摂取目標量は以下の通りです。
しかし、日本人の平均塩分摂取量は約10gとされており、ほとんどの人が目標値を超えているのが現状です。
塩分の過剰摂取が続くとおこる症状
日々の食事で塩分を適切に管理することが、健康維持につながります。
塩分計の基本的な仕組みと使い方とは


塩分計は、食品中のナトリウム濃度を測定し、塩分(食塩相当量)として数値化する機器です。特に、汁物や液体調味料の塩分濃度を測定するのに役立ちます。
デジタル塩分計の基本的な使用方法
※測定前の注意点
測定結果から実際の塩分量を計算する方法
塩分濃度と実際の塩分量の計算方法
塩分計が表示する「%」は、100gあたりに含まれる塩分量(g)を示しています。
塩分量の計算式
液体の重量(g) × 塩分濃度(% ÷ 100)= 塩分量(g)
具体例(味噌汁200mlの場合)
具体例(ラーメンスープ300mlの場合)
1日の塩分摂取目安(6g以下推奨)の約75%を1杯で摂取してしまう計算になります。
塩分濃度の基準
目安となる塩分濃度(汁物の場合)


0.6~0.8% → ちょうどよい減塩レベル
1.0% 以上 → 塩分高め!減塩を意識しよう
1.5% 以上 → 高塩分!注意!
一般的に、味噌汁やスープの塩分濃度は0.6~1.2% と言われています。1.0%を超えると塩分が多めになるため、できるだけ薄味を意識しましょう。
減塩対策
塩分の摂取量を管理するためには、塩分計の活用に加え、日常の食事で減塩を意識することが重要です。
最後に
塩分計を活用することで、食事に含まれる塩分量を数値で確認し、適切な減塩対策を行うことが可能になります。特に、腎臓病や高血圧が気になる方は、1日の塩分摂取量を意識し、適切な食生活を心がけることが健康維持につながります。
日々の食事で塩分を適切に管理し、健康的な生活を目指しましょう。
公開日:2025-3-26
更新日:2025-11-11