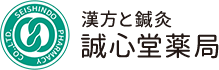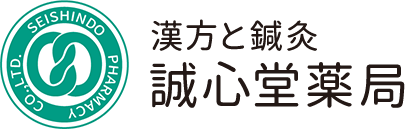五行人相学入門・序章
体と心を整える“養生”と五行の知恵
「なんとなく不調」に、どう向き合う?


年齢を重ねるごとに、「なんだか疲れやすい」「気分が安定しない」「冷えやすくなった」など、はっきりした病気ではないけれど、不調を感じることが増えてきます。
そんな“未病”の状態に、東洋の知恵「養生(ようじょう)」がそっと寄り添ってくれます。
養生とは、日々の暮らしで自分を整えること


「養生」とは、健康を保ち、病気を予防するための生活の知恵。
中医学では以下の2つの意味があります。
1.病気になる前に、生活習慣で心と体を整える(=摂生)
2.病気の回復期に、無理をせず体力を養う(=保養)
食べ物、睡眠、感情、動き方、人間関係……。
毎日の小さな選択が、未来の自分をつくっている。
それが、東洋医学の考える「本当のケア」です。
2000年前の教えに学ぶ「未病先防」という考え方


中国最古の医学書『黄帝内経』には、こんな有名な言葉があります。
「上医は未病を治し、中医は欲病を治し、下医は既病を治す」
これは
• 上医(優れた医師)は、まだ病気になっていない段階で整える
• 中医は、症状が出る手前で治す
• 下医は、病気になってから治療する
という意味です。つまり「未病のうちに整える=養生こそが最上の医療」と考えられていたのです。
人それぞれ「合うケア」は違う


現代では「このサプリがいい」「これが体に効く」といった情報があふれています。
でも中医学では、同じものでも“合う人”と“合わない人”がいると考えます。
例えば、体を温める人参は、冷え性の人には効果的でも、熱がこもるタイプには逆効果。中医学の言葉にこうあります。
人参が人を殺しても罪ではなく、大黄が命を救っても功績ではない
人参杀人无过,大黄救人无功
自分の体質を知ることが、最良のケアの第一歩なのです。
「五行」と「人相」で体質を知る
中医学では、人の体は五行(木・火・土・金・水)で構成されていると考えます。
この五行は、お互いに助け合い(相生)、制御し合う(相剋)関係でバランスを保ち、生命活動を維持します。
そして、人間の五官(目・鼻・口・耳・舌)や体型、性格、精神活動などにも、五行の優勢表現があらわれるとされます。
その表れ方によって、人は次のように分類されます。
| 金タイプ | 木タイプ | 水タイプ | 火タイプ | 土タイプ | 混合タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 「義」頭の回転が速い 現実主義者 |
「仁」正義感が強く 一本気なリーダー |
「智」柔軟性に富んだ 独創的な人 |
「禮」明るく聡明な アーティスト |
「信」誠実な のんびり屋さん |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 理知的でシャープ。正義感と秩序を重んじる | 伸びやかで上昇する性質。成長・変化を求める | 内向的で思慮深く、静かに深く流れるような感性 | 明るく情熱的。感情が豊かで発散型 | 穏やかで安定感がある。包容力のあるタイプ | 複数の五行がバランスよく現れる人も多くいます |
| ・やや細くて肌が白い ・顔の幅が広い ・肩の幅も広い ・顔が四角に見える |
・顔が細長い ・顎がとがっているけど肉付きがいい ・体は細長い ・太くなりにくい ・顔が逆三角形 |
・肉感 ・痩せにくい ・小さいころから全体的に肉付きがよい ・体が丸く見える |
・頭がとがっている ・顎がとがっている ・口が噴火のように見える |
・時に肥満になり時に痩せる ・体は大きく盛ん ・背部は分厚い ・首が短く見える |
この五行のタイプを読み解くヒントとなるのが「人相=顔」です。
「顔は体の鏡」—— 五行人相学とは?


顔の形、目の輝き、輪郭、肌の質感……。
それらには、五行の体質や気の巡りがあらわれています。
中医学の理論をベースに、顔から体質や気質、相性や養生法を読み解く知恵が「五行人相学」です。
これからの連載では、あなたの顔タイプがどの五行に当てはまるのかを見極めながら、
• 出やすい不調
• 季節ごとの注意点
• 相性の良い人相
• 自分に合った食事、運動、セルフケア
などをタイプ別にご紹介していきます。
“自分に合う整え方”を知って、あなたも「上医」に
「これがいいらしい」ではなく、「私に合っているか」が大事。
その選び方を身につけることが、今を健やかに、未来を美しく生きる鍵になります。
あなたの顔に現れている、五行の声に耳を澄ませてみませんか?
次回からは、それぞれの五行タイプに合わせた具体的な養生法をお届けします。
📅 公開日:
🔄 最終更新日: