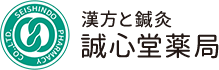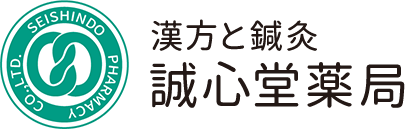妊娠中のトラブル「胎児発育不全」
◆胎児発育不全とは

胎児発育不全(FGR)とは、お腹の中にいる赤ちゃんが妊娠週数に対して成長が遅れ、標準的な発育が見られないものをいいます。
胎児発育不全と診断されると、胎児の健康リスクが高まり、赤ちゃんが病気や障害を持って生まれたり、死産となってしまうケースや、新生児期やその後の発育に影響を及ぼす可能性があるとされています。
◆胎児発育不全の診断

正常な体重で生まれる児の約95.4%はこの上下二本の曲線の間に入ります。
日本産婦人科学会「推定胎児体重と胎児発育曲線」保健指導マニュアルより抜粋
一般的に胎児体重基準値により、-1.5SD(標準偏差)値以下を目安に診断されていますが、1回の検査で小さめであったとしても、すぐに胎児発育不全と診断されるわけではありません。
胎児の発育の評価は、超音波による胎児の推定体重をもとに検査を繰り返し行い、子宮底長や羊水の量なども踏まえ総合的に判断することが大切です。
今後の検査で推定胎児体重が右肩上がりになっていれば心配なく、時間をかけて見守っていく必要があります。
子宮底長とは
妊娠中の胎児の成長と発達を評価するために使用されます。
恥骨結合の上縁から子宮底の最高点のところまでの長さを測定します。
最近は超音波検査のみで、子宮底長を測らないところもある様ですが、測り方の基準値は下記を参照にしてみてください。
子宮底長の基準値や、臨月の大きさの目安
子宮底長の基準値は、妊娠5ヶ月未満までは、「妊娠月数×3cm」の計算で求められます。
胎児の成長も早く、羊水量も増える妊娠6ヵ月以降は「妊娠月数×3cm+3cm」が基準値です。
お腹のふくらみがわかる妊娠4ヵ月ごろから測り始めます。

| 妊娠4ヵ月(12週~15週) | 7~12cm |
| 妊娠5ヵ月(16週~19週) | 13~15cm |
| 妊娠6月(20週~23週) | 18~21cm |
| 妊娠7ヵ月(24週~27週) | 22~24cm |
| 妊娠8ヵ月(28週~31週) | 25~28cm |
| 妊娠9ヵ月(32週~35週) | 28~31cm |
| 妊娠10ヵ月(36週~39週) | 32~35cm |
◆胎児発育不全の原因
赤ちゃんの発育への影響は、母体・子宮・胎盤・臍帯・胎児のどこに問題があっても起こります。
① 母体の原因
妊娠高血圧症候群
妊娠高血圧症候群ではお腹の赤ちゃんにうまく血液を送ることができないため、15~24%に発育不全が認められています。
他にも、糖尿病や腎疾患、膠原病などが原因になることがあります。
栄養の不足
もともと痩せていたり、極端なダイエットをしたり、妊娠中のつわりなどで栄養失調になったりすると、赤ちゃんの栄養が不足して成長が遅くなり、発育不全の原因となる可能性があります。
アルコール・喫煙
アルコールを多量にとると、赤ちゃんが胎児アルコール症候群となり、高度の発育不全や精神発達障害の原因となります。
喫煙においては、胎盤内の血流を低下させるため、吸わない人と比べて胎児の体重が5~9%減少することが報告されています。
② 胎児の原因
染色体異常
ダウン症候群や13トリソミー、18トリソミー、3倍体や45Xなど染色体異常による発育不全は全体の2~7%に見られ、妊娠の早期から発育不全が認められるものが多いとされています。
先天的な疾患・感染症
生まれつきの心疾患や、母体を通じて風疹ウイルスやサイトメガロウイルスなどの感染症にかかると発育不全の原因になることがあります。
多胎妊娠
胎児が2人以上お腹にいる場合、1人を妊娠しているのに比べて赤ちゃんの体重は少ない傾向があります。
発育不全が起こる頻度は、1卵性双生児で約30%、2卵性双生児で約20%とされています。
③ 胎盤・臍帯の原因
胎盤や臍帯の形態異常は、妊娠中の超音波検査で見つかることもありますが、見つけられないこともあります。 胎盤や臍帯の位置が悪かったり、ねじれていたりすると、血流が障害され栄養を送り届けることができず、低酸素・低栄養状態となり、発育不全や胎児機能不全(胎児心拍の異常)を発症するようになります。
◆胎児発育不全の西洋学的治療
残念ながら、胎児発育不全に対して効果的な治療法はありません。
母体の生活習慣の乱れによって起きている場合は、食生活の改善や喫煙といった生活習慣を見直すことにより、改善されることがあります。
安静に過ごすことで、できる限り赤ちゃんがお腹の中に留まり、大きく成長できるようにすることがとても重要です。
赤ちゃんやお母さんの健康状態が悪くなった場合には、早期分娩をすることもあります。
◆漢方で考える胎児発育不全への対策

クリックで画像拡大
中医学における胎児発育不全への対策は、発育不全にならないための取り組みであり、妊娠前・妊娠中の体質改善が大切です。
母体の「
気血水
」のバランスの乱れや、「腎気
」の不足、胃腸虚弱、ストレスや血行不良が原因になると考えられます。
漢方薬や鍼灸を通じて、個々の体質に合わせた対策を行い、赤ちゃんの健全な発育を目指していきます。
① 腎の虚弱体質<<腎精不足 >>
身体の状態:飲食の偏りや栄養不足により痩せている、胃腸虚弱、つわり、過労、出血性の病気、慢性病などにより、赤ちゃんを栄養するためのエネルギーである「気」や栄養となる「血」が不足している状態です。
方法:不足している「腎気」を補い、赤ちゃんを養うために「補腎安胎 」を行います。
|
漢方 |
亀鹿二仙丸、瓊玉膏、菟絲子、続断、杜仲など |
|
ツボ |
腎兪・関元・太渓など |
② 気と血の不足体質<<気血両虚 >>
身体の状態:飲食の偏りや栄養不足により痩せている、胃腸虚弱、つわり、過労、出血性の病気、慢性病などにより、赤ちゃんを栄養するためのエネルギーである「気」や栄養となる「血」が不足している状態です。
方法:胃腸を元気にして、不足している「気血」を補う方法である 「補気健脾」「 気血相補」を行います。
|
漢方 |
六君子湯、十全大補湯、帰脾湯、当帰、黄耆など |
|
ツボ |
三陰交・足三里・気海など |
③ 気と血が滞る体質<< 気滞血瘀 >>
身体の状態:精神的緊張・ストレス・プレッシャーや、運動不足、喫煙習慣などにより「気」や「血」の巡りに滞りが生じている状態です。「気血」の循環が停滞することで血行が悪くなり、赤ちゃんに栄養を送る力が弱くなっています。
方法:滞っている「気血」を巡らせる「疏肝理気 」 「行気活血 」を行います。
|
漢方 |
血府逐瘀丸、芎帰調血飲、当帰芍薬散、柴胡、延胡索など |
|
ツボ |
太衝、内関、血海など |
◆生活養生
胎児発育不全を未然に防ぐために、ご自分でできることに気をつけて過ごしましょう。
- ・定期的な妊婦検診を受けることで、妊娠が順調に経過しているかを確認しましょう。
- ・妊娠前にご夫婦で風疹のワクチンを打ちましょう。
- ・上のお子さんがいる場合は、唾液や尿などサイトメガロウイルスの感染に気をつけましょう。
- ・適正体重(BMI)を意識し、バランスの良い食事を心掛けましょう。
- ・妊娠したら、禁酒と禁煙をしましょう。
- ・睡眠は7時間を目安にして、身体に疲れが溜まらないようにしましょう。
- ・ストレスを溜めないようにしましょう。
- ・適度な運動をして血液循環を良くしましょう。
更新日:2024-05-28